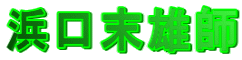
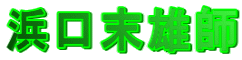
|
「大祭司の祈り」 浜口末雄 ヨハネは17章で、イエスの最後の祈りを紹介する。16世紀のプロテスタント神学者D・クリュテウスは、この箇所を「大祭司の祈り」と名付けたという。3つのテーマで祈られている。先ず、ご自分の栄光化を祈る(1〜5)。そして世に残る弟子たちのために、御父の保護を願う(6〜19)。最後に、ご自分を信じるようになるすべての人々のために祈る(20〜26)。彼らが1つになるように。 1.モーセの祈り 旧約の民の代表者は、いつも民のために祈っているが、モーセはその典型といえる。モーセに「好意を示し、名指しで選んだ」神は、彼に免じて民を救う(出33の17)。 モーセの召し出しの場面(出3)は、非常に現実味があっておもしろい。「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」はご自分が生きている神であるが故に、人も生きることを望まれる。神は苦しんでいる民を見るに見かねて、ご自分を顕わし、モーセを召し出す。彼はモーセを、ご自分の憐れみ深さを分かち持ち、ご自分の使者となるよう召し出す。いや、すでに以前からモーセの心に植え付けていたにちがいない。安定した生活を送っているモーセの心から、悲惨な同胞たちの姿が消え去ることはなかった。 しかし、モーセは、簡単には引き受けない。無理な注文だということは簡単にわかる常職人だからである。神は真剣に訴え、モーセはねばり強く抵抗する。その過程は召し出される者のすばらしい祈りである。彼は弁解し、そして何よりも、質問する。神はその質問に、ご自分の名を打ち明けて応える。神の秘密を打ち明けられたモーセは、「ちょうど人がその友人と語り合うように、顔と顔を合わせて」語り合うようになる。(出33の11)モーセは自分の使命に忠実であり続けるためにいのり、神の秘密を民に知らせる。 その後もモーセは、民の側に立ち、大胆にも神に抵抗する。 「主は彼らを滅ぼすと言われたが主に選ばれたモーセは破れを担ってみ前に立ち彼を滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。」(詩106の23) 神は愛であり、アーメンである。神はご自分の民を見捨てることはできないと、モーセは確信している。 |
|
2.王の祈り イスラエルの王は牧者であり、その民のために祈り、民の名において祈る。 ソロモンは、神殿の献堂式を司式して祈る。(1王8の10〜61)王は、両手を天に上げ、自身のため、全人民のため、そしてこれからの世代のために、罪の赦しと日毎の必要のために主に祈る。神殿はこれから、神の民の、祈りの場となる。「神殿には契約の箱があり、年毎にエジプト脱出を記念する。王はもちろん、民も、神の契約への忠実さに訴えて祈る。「あなたの約束通りに実行してください」と。イスラエルの祈りは、信頼に満ちている。人が、感情的な生き物である以上、祈りの場は大切にさるべきであろう。 3.詩編 王ダビデは祈りの人である。詩編の多くはダビデの作とされている。詩編には、聖書の全思想がささいな点に至るまで反映している。神の民は詩編を祈って、神の偉大な業、律法と掟、預言者たちの勧告、処世的知恵などを、感謝、賛美しながら想い出し、心に刻む。人々は、エルサレムに巡礼しながら詩編を歌い、神殿の大祝祭と、シナゴーグのサバト集会で詩編を祈る。詩編は神のみ言葉が祈りとなった書で、教会の祈りである。詩編作者ダビデの末であるイエスは、詩編で祈り、詩編を歌いながら十字架上で死んでいった。詩編は大祭司の祈りに相応しい。叙階によって牧者と定められた司祭は、詩編で祈ることを義務づけられる。詩編で祈りながら、祈ることを学び、神の秘密を知り、養われ、養われることによって自分の使命に忠実であり続けることができる。 4.祭司的民の祈り 新しい神の民も、詩編によって祈る。洗礼によって、祭司的民のメンバーに加えられたキリスト者は、自分のためにだけ祈ることは許されない。主の日にはミサに与り、キリストと共に全人類を代表していけにえを捧げる(奉納)。そしてお恵みを分配するために世に遣わされる(派遣、福音宣教)。 5.大祭司の祈り ヨハネ福音書によると、イエスは、最後の晩餐の後、どのように祈るべきかを教え、ご自分も大祭司として長い祈りを捧げられる。「今まであなたがたは、わたしの名によって何も願わなかった。願いなさい」(ヨハ16の24)と、教える。誰かの名において何かをするということは、その人と真のつながりがなければならない。キリストの名において祈るキリスト者は、キリストの心を心とし、キリストが願うことを願う。 イ=先ず、御子に栄光を与えてくださるようにいのる。すべての人を支配する権能を有する御子が、「ゆだねられた人すべてに、永遠の命を与えてくださいますように。」(17の2) ロ=弟子たちを「悪いものから守ってくださる」よう祈る。弟子たちは、そして信仰者たちも「この世の者」ではないが、未だ「この世」に留まっており、「悪いものから」守られなければならない。「ご自分の時が来たことを悟った」イエスは「世のいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれ」る。(13の1)よい牧者にとって羊たちは、この上なく愛し。命を投げ出すことさえいとわない。そしてその祈りに嘘はない。 ハ=最後にイエスは、未来の信仰者たちのために祈る。「すべての人を一つにしてくださるように。」(17の21)この一致には2つの次元がある。垂直の次元は、イエスと御父の関わりに基づく。水平の次元は、共同体のメンバー間の交わりである。この一致は、単なる人間的団結の表現でも、新しい共同体の組織化のプログラムでもない。それはイエスによる啓示であり、これを実現させることが彼の使命であり、そのためにこそ彼は派遣されたのである。唯一の神が父であることを知り、この御父の許に、すべての人が兄弟として集う。ここに救いがある。キリスト者はこの福音のメッセージを持って「この世」にチャレンジする。大祭司イエスの祈りは、十字架を担うことによって行動に移される。イエスに遣わされる者はもちろん、祭司的民も、イエスと同じ祈りを祈りながら「この世」に挑戦し続ける。 (長崎カトリック神学院) |
|
聖書に親しむ 「ゲッセマネにて」 浜口末雄 わたしはペトロです。 ゲッセマネで、わたしはご変容の時と同じように(マタイ17の1〜6)ヤコブ・ヨハネ兄弟と3人で、主のすぐ側に居ました。あの時のことは決して忘れることはできません。時間はまだその程遅くはなかったのですが、すごい睡魔に襲われて、主のおことばもわずかしか聞き取ることができませんでした。言い訳がましいようですが、わたしの時代はまだ電気も、テレビもなかったし。それに農・漁業のために朝が早いので、夜はできるだけ早く休むのが当時の習慣でしたから、特にその日、わたしたちは旅の疲れでどうにも我慢できなかったのです。ご自分といっしょに「目を覚ましているように」(38)言われました。今になって思うと、主が明らさまにご自分の動揺を打ち開けられて、わたしたちに助けを求められたのはそれが最初で、最後でした。その時はしかし、主がどれ程大きな内的苦しみに逢われていたか、わたしたちはわからなかったのです。共に苦しむよう召し出されたのに。 その夜、つまり「種なしパンの祭りの第1日に」(17)「町のあの人の家で」(18)過越の食事を済ませ、宿を取っていたベタニアへ向かいました。わたしたちは都へ上がったときはベタニアに宿を取るのが普通でした、そしてその行き帰りはいつもオリーブ山の道を通っておりました。もちろん裏切ったユダも(わたしも裏切ったのですが)このことは充分承知しておりました。ケデロンの谷を渡り、オリーブ山の西側のスロープの中腹、ゲッセマネ(「油しぼり」の意)という園に付きました。ここは、現在フランシスコ会の教会が建っている辺りですが、主はよくここでお祈りをしていましたので、(ルカ22の39・40)その夜も祈るために園に入って行かれました。主は他の人たちをそこに残し、わたしたち3人だけを連れて更に中に入って行かれました。主は、わたしたちのすぐ先でお祈りを始め、「死ぬ程悲しみもだえ始めた」(38)のにわたしたちは居眠りを始めたのです。 主がその時、どのようなことを考え、どれ程の激情に駆けられていたのか、今だに充分は理解し尽くすことができません。福音書には下手な解説をするよりも、と思って、睡魔と闘いながらではありましたが、近距離から見て、聞いたことだけを報告いたしました。でも今日は少したち入って考えてみたいと思います。死が追っていました。しかも十字架の死です。主はすでにこのことをよく知っておりました。わたしたちは主がメシアであり、ダビデ子であると信じていましたから、つまりダビデの王座に着く主であると信じていましたので、まさかあのような形で死ぬとは最後の最後まで考えませんでした。でも主はずっと以前から覚悟していたようです。ベタニアで食事をしている時でした。一人の婦人が入って来て、主に高価な香油を頭に注いだのです。大宴会の時はそんな習慣があるにはあったのですが、その時の食事はごく普通の食事でしたし、何よりもその香油が高価すぎたのです。生活のためにいろいろと不自由を強いられていたわたしたちは怒りました。誰よりも質素を好まれた主も、当然怒るだろうと思ったのですが、主は許されたのです。頭に香油をうけながら差し追ったご自分の死と葬りとを考えておられたのです。(6〜13)過越の食事の時もそうでした。ご自分の死と復活の記念として聖体を制定され「これがあなた方と供にする最後の晩餐である」と言われたのです。(26〜29) 主はずっと以前から死を覚悟しておられたのですが、われわれ人間と同じように、それまでは死をそれ程身近じかに感じられることはなかったろうと思います。幸いなのでしょうか。不幸なのでしょうか。死に直面した人さえ一度死の危険を乗り越えると、もうそのことは忘れてしまうのです。今、主は「その時」を迎えました。最期の試練の時を迎えたのです。お酒好きがお酒を飲みたいような誘惑ではありません。凡人が迎える死の苦しみとも質が違います。聖書独自の思想で、終末論的試練、メシアの試練です。生みの苦しみ、救いの新時代を実現するために経なければならない試練です。ゲッセマネはまず心理的試練でしたから、これを心理的に乗り切らねばなりませんでした。神に近づけば近づく程神は人間を試みられます。(ユディト8の25〜27)アブラハムはひとり息子イサクを犠牲にせねばならなかったし、ヨグも、すべてを奪われ、長い間死線をさまよわなければなりませんでした。神の現存を身近に感じる義人にとって、そのうける試練は理解し難く、不条理であり、この上なく苛酷なものです。選民イスラエルは約束の地に入るために砂漠を通いました。シナイは、昼間は熱さのたまにパーン、パーンと音を立てて岩が割れるといいます。冬場にもなると夜は凍傷になる程の厳しい寒さだといいます。またイスラエルは、新しい契約共同体形成のため捕囚を経験しました。戦火で多くの者は死に、残された者は、「情に富んだ女の手さえ、自分の子を煮る」(哀歌4の10)ほどでしたし、捕囚の人々も「バビロンの川岸に座し、シオンを思って泣き」(詩篇137の1)ました。 神の子は神の僕として(イザヤ52の13〜53の12)神の子羊として(出エジプト12の5)決定的神の国現実のため十字架の死を受け入れます。できれば「この杯」を避けて通りたかった。神は他の方法でも人類を救うことがおできになるはずです。もう難を逃れることはできないのだろうか。これまでチャンスはしばしばあった。でも主は危険な都エルサレムへご自分から先頭を切って進んで来られたのです。(マルコ10の32)陰謀者たちは、主の処刑を「祭の間はいけない」と考えていました。(マタイ26の5)ところが彼らの意に反して事は着々と進んで行きました。すでに裏切りの報酬を受けて、引き渡しのチャンスを窺っていたユダを出発させたのは主でした。(マタイ26の25)まさに出来ごとのイニシアティブは、主ご自身が握っておられるような観がありました。ゲッセマネの死ぬ程の苦悶でも、それまでと同じ態度を貫き通しました。主は捕らえられたのではなく、御父のみ旨にどこまでも忠実を尽くし、ご自分から勧んで十字架を担われたのです。 主はゲッセマネの苦悶の中で、3重の貴重な体験をされました。 「この杯」を逃れようという強い誘惑。日常の誘惑を超えるこの種の誘惑に、生身の人間は決して打ちかつことはできないということを、主はご存知でした。(マタイ24の22)ですからかつて、主の祈りの中でも「誘惑に陥らないように導き、悪から救ってください」(マタイ6の13)と祈るよう諭され,この時も、「誘惑に陥らないように、目を覚まして祈りなさい、心ははやっても、肉体は弱いものだ」(マタイ26の41)とわたしに諭されました。逃れようとの強い誘惑の中で、主は、十字架を執るべきであるとの声、ご自分の霊、聖霊の力強い声を聞くことができました。 聖霊は特に試練の中で力強い働きをなさいます。「信仰の試しは忍耐を生み、忍耐は業によって完成されます。こうして(聖霊は助けによって)完全な者、出来上がった者、不足のない者となるのです。ですからいろいろな試練に会うときにはそれをもっとも喜ばしいことだ」(ヤコブ1の2〜4)と思って立ち向かうことができるのです。試練の中で、聖霊が解放の働きを行い、人間は試練を通して内的過越の道、希望と愛の道をたどるのです。(ローマ5の3〜5) 聖霊の導きにより、御父のみ旨に従った主は、こうして完全な、最高の自由を体験することになるのです。アダムは自由を与えられましたが、自己本位の道を選んで滅びを体験しました。(創世記3)主は極度の試練の中で愛の道を選んで御父神との決定的一致を体験しました。主は「そのためにこそ、この時を迎えた」(ヨハネ12の27)のでした。「立て、さあ行こう」(マタイ26の46)と言われました。はじめ、「わたしと共に目覚めていなさい」(マタイ26の38)と言われても、眠りこけてしまったわたしたちに再び、「(十字架を執ってカルワリオへ)いっしょに行こう」と言って下さいました。この召し出しにもわたしたちは応えることができませんでした。でも、今からでも遅くはないと思っています今からでも、ゲッセマネへも、カルワリオへもお供できると確信しています。洗礼によって復活の生命へ召されたわたしたちは、同時にゲッセマネ、カルワリオへも招かれているのです。わたしたち人間生活の本質的部分にまで入り込んでいる苦難は、ゲッセマネにおいてその正体を表しました。試みは、サタンがこれを利用して、自己本位と絶望へと引き込む誘惑の機会でもありますが、神に対する信仰、希望、忠実、人間の自由を開花させ、強める絶好の場でもあるのです。聖霊があらゆる試練の中でいつも働いて、神から 離れた状態から神との一致の状態へ、自己本位の生活から愛の生活へ、そして最後は、最大の試練である死を、主と共に通過することによって、復活の生命へと過ぎ越して行くのです。過越の祭を終えた一団がゲッセマネへ近づいておりました。わたしたちは、ほとんど完全に眠り込んでおりましたので、すぐ近くに来るまで気付きませんでした。でも主だけが、再び平静を取り戻して、たいまつの行列を為して近づく一団を眼下に見ていました。 (大曽教会・主任司祭) |
|
聖書に親しむ「ルカによる十字架の道」 浜口末雄 「すでに昼の十二時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿のたれ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます。」こう言って息を引き取られた。 イエスの逮捕から、十字架の壮絶な死までを取り仕切り、その一部始終を見守っていたローマ軍一個師団長・百人隊長は、この出来事を見て、「本当に、この人は正しい人だった」と言って、神を賛美した。 そもそも事の始まりから通常とは変っていた。 エルサレムの治安の任に当たっている自分のもとに訴え出たのは、ユダヤの権威者たちだった。告訴の理由も、ローマに謀反を企む首謀者だということであった。これまでユダヤ人から、この種の訴えを受けた覚えはない。かえってファリサイ主義の人々は、自分たちが容疑者の捜索をしようとすると、邪魔だてさえしてきた面々である。いつもは仲の悪いファリサイ主義の人々とサドカイ主義の人々とがこぞって、しかも憎悪を顕わにして訴え出たにである。イエスという人物は、ローマ官憲のブラックリストには載っていない。しかし噂は聞いている。なんでもガリラヤ分国王ヘロデが処刑したヨハネが、一目二目も置いた同僚だという。ヨハネといえば、ヘロデの結婚問題に堂々と一撃を加えた男である。そのヨハネが尊敬して止まない人物であれば、おそらく筋金入りであろう。しかし政治的な問題は見えてこない。 ねらいは一人だし、居場所もはっきりしているから、正規の軍人が2・3人もいれば十分だった。ところが出発しようとするとユダヤ人の神殿守備隊が剣や棒を手に、ぞくぞくとついて来る。おまけに祭司長や長老たちまで。先導したのは、イエスを裏切ったユダだった。 逮捕は簡単だった。 オリーブ山に着くと、十数名の野宿の集団があった。その中のひとり、立ってこちらを見守っている人物に、かねての打ち合わせ通りユダが近付き、接吻しようとした。事態は把握しているはずである。武装集団が回りを取り囲んでいる。近付いてくるユダが裏切ったのは火を見るより明からだ。落ち着きはらって、あわてず、かえって哀れみ深くユダを拘擁している。まわりの男たちはハチの巣をつついたようなあわてぶりである。それでも勇敢なひとりが、大祭司の手下に切りかかって、その右の耳を切り落とした。一瞬、緊張が走った。緊迫した空気を破った、当のイエスだった。「やめなさい。」いきり立った男を静止して、しかも負傷した男を介抱してくれている。そして自分の方から両手を差し出した。 ユダヤ人たちは、異常と思えるほどの憎しみをもって、一晩中イエスをいたぶり、暴行を加えた。 翌朝、ユダヤ人の最高法院で宗教裁判が開かれた。イエスが自分のことを「メシア」とか、「神の子」とか言ったか言わなかったかが問題となった。かれらの法では、神への冒涜罪は死刑に当たるらしい。イエスは命乞いどころか、弁解さえしない。ピラトの尋問でも、その威厳に満ちた態度は変らない。ユダヤ人たちは、人民を惑わし、皇帝に逆らうものとして告訴した。さすがにピラトはプロの裁判官である。イエスの無実を確信した。ところがこの判決に、民衆が騒ぎだした。群衆心理とは恐いものである。なにが起こるかわからない。祭りが近いため、国粋主義者たちが国外からまで結集している。ピラトは、とうとう判決を翻した。 兵士の悲しさである。無実とわかっていても、決定は従わなければならない。遠い辺境の地で、つまらないことに関わって、やっと手に入れた百人隊長の職を逐われでもしたらたいへんだ。兵士はただひたすら任務を遂行するのみだ。 いつもの死刑執行の手順どおり、まずムチ打ちで体力を消耗させた。夜を徹した暴行のせいだったろうか、囚人が運ぶはずの十字架の横木を担ぐことさえできない。通りがかりのシモンというキレネ人を捕まえて、イエスの後から運ばせた。 道中、また不思議な光景を目にすることができた。 ガリラヤからイエスに同行した婦人たちであろうか、それともエルサレム在住の心のやさしい婦人たちであろうか、精魂尽き果てたイエスの姿を見て、同情し、嘆き悲しんでいた。イエスは、「わたしのために泣く必要はありません」と、声をかけ始めた。むしろ自分のことを、そして自分のこどもたちのことを心配するように、と言う。この人はだれからも慰めてもらう必要はないのだろうか。なぜ?苦しみの極みにありながら、まだ他人のことを心に掛けることができる。なぜ?さらに衝撃的なことが起こった。 それは十字架に釘付けしている最中である。事務的で、慣れて手つきではあるが、3人もの人間の処刑である。死刑執行者たちは興奮気味だ。イエスがなにかつぶやいている。祈りだ。祈りをしている。「父よ、かれらをお赦しください。自分がなにをしているか知らないのです。」この人は、自分に敵意をもっている人を赦すことができる。温かく迎えることができる。しかも、この極限状況で。 議員たちも、兵士たちも嘲笑い、侮辱していた。「おまえがユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。」「他人を救ったのだ。もし神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい。」神は救いに来てくれるだろうか。自分が神なら、この人を救いたい。 犯罪人のひとりも同じようにののしっていた。「おまえはメシアではないのか。自分自身とわれわれを、救ってみろ。」もうひとりの方は彼をたしなめていた。「おまえは神をも恐れないのか。われわれは、やったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方はなにも悪いことをしていない。」「イエスよ、罪深いわたしを哀れんでください。」イエスはこの犯罪人の願いを聞き入れ、天国を約束してくれている。自分の欲のために国を売り、何人もの人を殺害し、人間の心を無くしてしまったこの犯罪人が、最後の最後に、わずかに人間らしい心を取り戻したら、即刻この人を受け入れている。いや、今受け入れたのではなく、敵をも赦すこの人の方が、先に犯罪人の心に入り込んでいたのだ。 いよいよ最期が来た。 午後3時ごろだった。ぐったりとなって、うなだれていたイエスは、おもむろに天を仰いで、まるで勝ち誇ったように、「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます」と言って、息を引き取った。 助けに来なかった神に、最後の最後まで沈黙を守り続けた神に、まだ「父よ」と、呼び掛けた。この人は、ことがすべて神の御手のなかで起こったと信じきっているのだ。悪に悪をもって報いることなく、かえって善をもって対処することによって人々とのコミュニケーションを確立しようとしたのに、そしてこれに命を賭けたのに、人々はこれに応えることができなかった。人間の限界なのだろうか。彼の使命はここにあったのだ。彼はこの使命に常に忠実であった。そして十字架の道は、その使命に生きる彼の神秘が顕現する最高の機会となったのだ。彼は死んだが、実は最高に生きたのだ。世は彼を受け入れなかった。受け入れることができなかった。しかし彼は信じている。神が自分の使命を完成してくれることを。彼と神とのコミュニケーションは途絶えることは無かった。子としてのユニークな対話は続いていたのだ。 「本当に、この人は神の子であった。」 |
|
よきおとずれ 2002年5月1日 神学生養成に関わって 浜口末雄 10年前にも及ぶ小神学校での神学生養成の任務なんとか終えることができました。その間、たくさんの方々から、いろいろな形でご援助をいただきました。非受洗者を含む教養講座の先生方、お米や野菜などの生活物資を定期的にご援助くださった方々、本当に目の玉が飛び出るほどの現金を援助くださった方々に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。神学生と保護者の皆さまには、感謝と同時に、おわびを申し上げます。力不足のため、ふさわしい指導を施すことができず、申し訳ありませんでした。神学生養成担当を終えるに当たり、2・3、所感を述べさせていただきます。 1.小神学校不要論 自分にも経験があるが、入学して最初に乗り越えねばならない山がホームシックである普通、数回の涙で始まる。最近は3,4年の長期に及んだり、頭痛、腹痛を伴う重傷であったりする場合がある。一般的にも、精神年齢の低下が指摘されているが、豊かさに伴う生活形態の変化の結果ではなかろうか。かといって高校生から志願者を募ろうとすれば、これまでは5年に1人の割合でしか希望者は出てこない。このような時代、家庭で召命の恵みを温めながら反抗期を乗り越えることは至難の業ではないか。12歳という年齢に、幼児期に要する母性愛が必要なのだろうか。むしろ切り離して自立を促す方が本当ではなかろうか。 2.召命意識 入学してくる神学生の意識には差がある。相当な決意にある子もいるが、いわゆる「初志貫徴」には幼すぎる。どのように召命を温め、育てていくか神学生本人同様、養成者の勝負どころではある。小神学生も、召命が「神さまの呼びかけ」であることは、教えられて知っている。しかしそれを自分の希望、気持ちと同一視すること以外に理解することができない。「ミュージシャンになりたい」「医者になりたい」…それが自分の召命だと言って退学していく。「自分の考えでなく、御父のみ旨を行う」キリストを理解することは難しい。小神学生養成の第一の目標は、神と語らう祈りのできる信仰者の育成である。 3.すそ野を広げる 司祭召命は成熟した教会から生まれる。召命減少の責任を、少子化という自然現象のみに負わせてはならないと思う。大人を含めたカテケジス、家庭、結婚など、あらゆる分野でテコ入れが必要ではないか。お恵みに信頼しながら、司祭を含めて全教区民に真剣に考えていただきたい問題だと思います。 (前長崎カトリック神学院院長、福江教会主任司祭) |
|
カトリック教報 昭和63年12月1日 教会見て歩き 大曽教会(上中五島地区) 大曽小教区(浜口末雄師)は、上五島海上石油備蓄基地として話題を呼んだ その中で大曽教会の歴史は古い。キリシタン弾圧のきびしい時代、外海地方より移住した信徒たちは、禁教令が解かれた6年後、1879年(明治12)大曽裏迫に初の教会を建設、その後1916年(大正5)現在の教会を献堂した。 1951年(昭和26)鯛之浦小教区より分離、大曽教会が設立され、現在に至っている。大曽教会の信徒戸数は約7百世帯。大曽全地区がカトリック信徒である。信徒家庭の世帯主の約80%が漁業に携わっている。 教会運営は評議会が中心で ? パワーも頼りになる存在である。 信仰深い信徒たちは昔と変わりなく教会中心で生活のリズムができている。 浜口神父は「信徒たちは維持費のほかに不時の出費に備えて、毎月3千円の積立をしています。不漁が続いている時なので決して楽な出費ではないと思いますが、とくに不満の声も聞きません」と話す。 |
 |
|
|---|---|
 |
 |